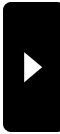2022年05月07日
トビイロシワアリからムシヒキアブの死骸を奪うクロヤマアリの動画をup
 クロナガアリの飛行に出会えないまま5月になった。
クロナガアリの飛行に出会えないまま5月になった。昨日は多くはないがヤマトシロアリの飛行があって様々な生物が恩恵を受けたみたいだ。
庭の草刈りをしつつ動画を撮った中での1シーン。
庭を飛び交うムシヒキアブもそれぞれがシロアリを捕えていた。
方や死んでアリに引かれるムシヒキアブも。
死骸が干からびていないことから死んで間もないことがうかがえる。
やけに体の柔らかいのだが、ムシヒキアブに吸われたあとは消化酵素の影響なのかこんな風になってることが多い。
ひょっとしたら共食い果ての姿かも知れん。
動画はこちらから ↓
https://youtu.be/NtQvZS505eE
2020年06月28日
トビイロシワアリの動画をup&近況

軒先にコガタスズメバチが営巣してたのを撤去して庭に放置。
トビイロケアリも来ていたがトビイロシワアリが上手く独占してた。
滅多にないごちそうに大盛況の様子を動画に撮った。
外部光源の具合も試したのだが曇天でもまずまず明るく撮れてる。
動画はこちらから ↓
https://youtu.be/i300DCw2yoA
ブログの更新もかなり間が空いた。
春から今までの女王の採取が全部できなかった。
クロナガアリは条件の良い日を外したみたい。
クロオオアリ、ムネアカオオアリは「飛ぶなら今日!」って日に行けなかった。
夜間飛行があるかも?って日に行ったがオスアリのみだった。
クロヤマアリも大小を捕獲したかったが梅雨の合間の良さそうな日に園地にいっても収穫無し。
アメイロアリには出会ったが道具を持ってなくて素手で傷つけてしまった。
う~む 今年は石膏巣も新調したのに。
何かタイミングが合わないんだよな
2020年04月13日
トビイロシワアリに滅ぼされたオオズアリの動画をup
 前回の記事”庭に放したオオズアリが滅ぼされた”の様子を動画に撮っていた。
前回の記事”庭に放したオオズアリが滅ぼされた”の様子を動画に撮っていた。先ほど編集し終わってupした。
このブログを始めた頃、庭には園地から捕ってきた7つのコロニーのオオズアリが数年間定着していた。
トビイロケアリの大コロニーが出来て次々に滅ぼされて見なくなった。
久し振りに定着を試みたがトビイロシワアリにあっけなく滅ぼされた。
上手く行かんな~。
動画はこちらから ↓
https://youtu.be/MnC4IT2GNIU
2020年04月11日
庭に放したオオズアリが滅ぼされた
2017年10月27日
クロナガアリの初期巣が5年ぶりに庭にできた

クロナガアリを庭に定着させようという試みを毎年のように行っている。
今年も数匹の女王を採取してきた。
他種に襲われないように円筒ケースに入れて、それを地面にひっくり返して様子を見た。
翌日には無事に土を掘って潜りこんだ。
でも大概は滅びてしまうようで秋にワーカーが観察されることはない。
今年は秋にワーカーが採餌活動をするところまでは成功した。
初期コロニー特有の小さめのワーカーが種子を集めている。
たぶん巣内には数十匹のワーカーが居そうな感じ。
2012年11月20日に庭にクロナガアリが定着した記事を書いている。
2013年5月12日にはそのコロニーが活動せず定着失敗した記事を書いた。
5年前に比べて近隣のクロヤマアリのコロニーが無くなって、トビイロケアリが衰退気味っていう状況の違いはある。
トビイロシワアリは相変わらず盛況だが。
来年の秋、一回りサイズが大きくなったクロナガアリのワーカーが活動している・・・かも知れん。
2015年06月02日
トビイロケアリ 翅アリ生産中(動画あり)
2014年12月13日
庭でクロニセハリアリ

11月下旬に庭で土いじりをしていて見つけたハリアリ。
体長は2.5mmほどの小型種。
この大きさで黒いハリアリはヒメハリアリかクロニセハリアリ。
ハリアリ属とニセハリアリ属の同定には
>腹柄節下部突起の前方部には透ける“窓”(光が透過できる小孔)
があるかどうかっていう分岐がある。
これが<無い>ことの確認がすごく難しい。
<有る>確認の方が簡単そうだ。
固くなったサンプルをアルコールで戻してあちこちから眺めたけど窓が見えないのでクロニセハリアリと同定。
写真が上手く撮れない。
ボタンを押すだけでピントがずれる。
続きを読む
2013年11月29日
古い動画 アズマオオズアリとオオズアリをUP
パソコン関連を整理していたら古い動画を居つけた。
編集してupしてみたけど・・・
アルミホイルを使った照明板も使っているが暗い。
それ以前に機材が古すぎて画像が荒くて残念。
観るためには想像力も必要かも。
バタークッキーにアズマオオズアリが先行して集まった。
やや離れた位置に巣があったオオズアリも察知して駆けつけて機動力を活かして餌を運びだして行く様子が映ってます。
アズマオオズアリとオオズアリの兵アリがバッティングする場面も。
2013年07月09日
4種競演
本日20時ころ、家の外灯にトビイロケアリ・ウメマツオオアリ・ヒラズオオアリ・アメイロケアリの4種が飛来しました。
昨日も暑くて蒸した夜なのに飛来は無し。
昨日よりももっと暑い夜となったが昨日よりも乾いた印象の今日、久しぶりに見る競演となりました。

シルエットでもそれと分かる特徴的なヘッドのフォルム。
警戒しながらも、じっとしている時間が長いので他種よりも撮り易い。

ヒラズオオアリのオス。
とても華奢な感じに見える。
尖り気味の紡錘形の尾部にオオアリ属の特徴を有している。
せっかく沢山飛んでいるんだから雌との2ショットとか、
ウメマツオオアリのオスとの近接写真とかを撮りたいのだが上手く行かず。
ウメマツオオアリのオスは一回り大きくて色も黒い。
トビイロケアリのオスはもう少しずんぐりして尾端の形状も違う。
アメイロケアリ亜属のオスは翅に黒い部分があるのでトビイロケアリのオスとはすぐ見分けが付く。
この辺りも画像で分かりやすく提供できればと思う。
こんな分析力を得るのにも何年も掛かった。
ネットで情報を提供してくれる方々に改めて御礼。
後はフィールドで現物と見比べて経験を積むしかない。
昨日も暑くて蒸した夜なのに飛来は無し。
昨日よりももっと暑い夜となったが昨日よりも乾いた印象の今日、久しぶりに見る競演となりました。

シルエットでもそれと分かる特徴的なヘッドのフォルム。
警戒しながらも、じっとしている時間が長いので他種よりも撮り易い。

ヒラズオオアリのオス。
とても華奢な感じに見える。
尖り気味の紡錘形の尾部にオオアリ属の特徴を有している。
せっかく沢山飛んでいるんだから雌との2ショットとか、
ウメマツオオアリのオスとの近接写真とかを撮りたいのだが上手く行かず。
ウメマツオオアリのオスは一回り大きくて色も黒い。
トビイロケアリのオスはもう少しずんぐりして尾端の形状も違う。
アメイロケアリ亜属のオスは翅に黒い部分があるのでトビイロケアリのオスとはすぐ見分けが付く。
この辺りも画像で分かりやすく提供できればと思う。
こんな分析力を得るのにも何年も掛かった。
ネットで情報を提供してくれる方々に改めて御礼。
後はフィールドで現物と見比べて経験を積むしかない。
2013年05月12日
庭のクロナガアリ 定着せず
前記事は2012年11月20日付け 庭にクロナガアリが定着した。
しかし春になっても巣口を開けた様子も無く、一向に地表での活動が見られない。
どうも何かに滅ぼされたようだ。

2週間前に飼育していたクロナガアリで規模の小さいコロニーを庭に出してみた。
庭の中でも日当たりの良い草地を選んだ。
円筒石膏巣を逆さに置いて外敵の侵入を防ぎつつ巣穴を彫らせる作戦。 続きを読む
しかし春になっても巣口を開けた様子も無く、一向に地表での活動が見られない。
どうも何かに滅ぼされたようだ。

2週間前に飼育していたクロナガアリで規模の小さいコロニーを庭に出してみた。
庭の中でも日当たりの良い草地を選んだ。
円筒石膏巣を逆さに置いて外敵の侵入を防ぎつつ巣穴を彫らせる作戦。 続きを読む
2012年11月20日
庭にクロナガアリが定着した

前記事は4/24に採取したクロナガアリの経過。
>5つのグループに分けたうちの一つは庭に住まわせた。
>構成は脱翅雌4匹。
>放した場所の近くにトビイロシワアリのコロニーがあるが、邪魔されること無く土中に潜り込んだ。
1ヶ月ほど前にワーカーを発見。
気に掛けて観ていてもワーカーの活動がほとんど見られない。
極たまに1~2匹が巣穴の周りにいるのをやっと写真に撮れた。
続きを読む
2010年08月16日
自然環境のコロニーが壊滅する病気ってあるのかな
庭の西側の一角を占拠していたトビイロケアリのコロニー。
アズマオオズアリのコロニーを壊滅させた記事でも紹介したが今年で丸6年の発達途中のコロニーだった。
アメイロケアリの飼育の為にワーカーや繭を失敬したが、今年は何だか占拠する庭の範囲が狭くなっていくように見えた。
7月の末頃には地表に全く姿を見せなくなった。
7月31日の記事にも書いたようにアメイロケアリに導入したワーカーも次々死亡している。
2つの現象には関連があって強力な病気が流行ったと思える。
庭のトビイロケアリのコロニーの跡地にはさっそくクロヤマアリが分巣を作り始めた。
クロヤマアリにとっては6年ぶりの失地の回復だ。
できればアズマオオズアリが飛んできてコロニーを作ってくれたら嬉しい。
トビイロケアリのもっと発達したコロニーが庭の東側にもある。
そちらのコロニーは元気で、寄生種用のワーカーや繭の調達はそちらからもできる。
さっそく竹筒トラップを用意しなくちゃ。
アズマオオズアリのコロニーを壊滅させた記事でも紹介したが今年で丸6年の発達途中のコロニーだった。
アメイロケアリの飼育の為にワーカーや繭を失敬したが、今年は何だか占拠する庭の範囲が狭くなっていくように見えた。
7月の末頃には地表に全く姿を見せなくなった。
7月31日の記事にも書いたようにアメイロケアリに導入したワーカーも次々死亡している。
2つの現象には関連があって強力な病気が流行ったと思える。
庭のトビイロケアリのコロニーの跡地にはさっそくクロヤマアリが分巣を作り始めた。
クロヤマアリにとっては6年ぶりの失地の回復だ。
できればアズマオオズアリが飛んできてコロニーを作ってくれたら嬉しい。
トビイロケアリのもっと発達したコロニーが庭の東側にもある。
そちらのコロニーは元気で、寄生種用のワーカーや繭の調達はそちらからもできる。
さっそく竹筒トラップを用意しなくちゃ。
2010年06月24日
アメイロケアリ いつでも来なさい

そろそろアメイロケアリの飛ぶ季節です。
寄生種は脱翅雌を採取したら寄生先をセットしなければ飼育できない。
で、庭からトビイロケアリを捕ってきました。
その前に2008年から飼育していたコロニーは壊滅です。
今年の3月なんですけど。
トビイロケアリのワーカーがバタバタと死に始めたら、アメイロケアリの女王が・・・

アメイロケアリのワーカーは、まだ残っていたのに。
何か病気が流行ったみたいです。 続きを読む
2010年03月03日
ヒラフシアリのコロニー

庭木の手入れをしていてヒラフシアリを見つけた。
最初は地上から50cmほどの生木の小さなウロの部分。
木屑のカバーを壊したら中にいた。
女王が見つかるかと期待しながらウロの部分を開いたが見つからず。
続きを読む
2008年11月11日
アジサイの枯れ枝からアリを採取してみる

枯れ枝には様々な樹上営巣種のアリが住み着く。
気温が下がるとアリの活動が鈍って逃げ足が遅いので採取がしやすくなる。
アジサイは芯がスポンジ状になるのでハサミがあれば枯れ枝を暴くのが簡単だ。
山あいではイタドリなど芯が空間になる植物も多い。
庭のアジサイの枯れ枝をを少し折ってみた。
最初に出てきたのはヒラフシアリ。 続きを読む
2008年11月08日
栄華盛衰(アズマオオズアリ)

良い写真が無いかと写真をあれやこれやと探していて過去ファイルから掘り出したもの。
庭のアリの記録です。
撮影は2006年4月18日の午後。
春に活動を始めたアズマオオズアリとトビイロシワアリがさっそく勢力争いを始めました。 続きを読む
2008年10月29日
クロヤマアリを襲うアミメアリ

本に載せる写真を探していて過去のファイルから引っ張りだしてきた写真。
撮影は2006年5月である。
写りが悪くてボツにしたが行動観察としては面白かった。
庭のクロヤマアリの巣を襲うアミメアリ。
本体からの分流した隊列がたまたまクロヤマアリの巣に行き着いてしまったのか。
新しい仮営巣地を探して斥候が発見して導いたのか。
発見したときにはアミメアリ達がクロヤマアリの巣に進入して次々にクロヤマアリの死体を運び出すところだった。 続きを読む
2008年07月30日
イガウロコアリ発見
庭の観察用オオズアリのコロニーが引越しして、その場所から更に引越しした先を突き止めている最中に梅ノ木の根元を歩いているウロコアリっぽいアリを見つけた。
ウロコアリにしては大アゴが短いではないか。アゴウロコアリ属か。

日本産アリ類画像データベースを見てみると18種類に分類されている。
比較的近年に種として分類された物が多い。
こんな小さく類似したグループの外見上の差異でよくぞここまで分類したものだ。
先人達の苦労が想像できていつもながら感心してしまいます。
続きを読む
ウロコアリにしては大アゴが短いではないか。アゴウロコアリ属か。

日本産アリ類画像データベースを見てみると18種類に分類されている。
比較的近年に種として分類された物が多い。
こんな小さく類似したグループの外見上の差異でよくぞここまで分類したものだ。
先人達の苦労が想像できていつもながら感心してしまいます。
続きを読む
2008年03月05日
竹トラップを直した
2008年02月25日
竹トラップを割ってみる

昨年冬に庭に沢山の枯れ竹を放置してきた。
越冬時にはどんなアリが竹筒を利用しているのか割ってみることにした。
大体の見当は付いている。
一番の期待は毎年玄関の外灯に飛来するヒラズオオアリのコロニーが何かの間違いでも入っていないか・・・なのだが。
庭から集めた枯れ竹を数えたら23本。
こんなに置いたっけ?
大半が竹林から拾い集めて持ち帰ったものだ。
続きを読む